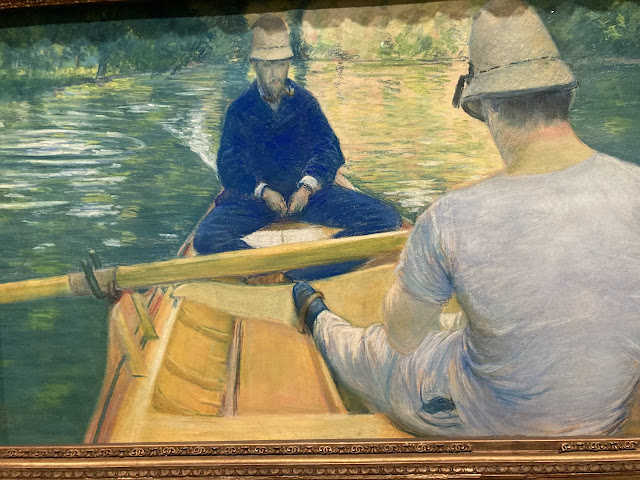テキスタイルアート?ってのはは大雑把に「布と糸を素材とするアート」でいいのかな?織ったり縫ったり紡いだり、もしくはほどいたり染色したり、伝統的に女性の携わってきた仕事あるいは職人芸という概念を免れえない。だから現代アートではそれに反発して女性問題の提示するとか、職人的技術を否定したラフなテクニックで表現されることが多いような気がするが、今カルチエ財団で大回顧展が開かれているオルガ・デ・アマラル
Olga de Amaral
は先に述べて伝統的な意味でのテキスタイルをいかにアートに昇華するかに腐心してきた作家と言えよう。素材も綿、麻から馬のたてがみ、そして金箔やパラジウム、それにプラスチックと様々な素材を導入。新たな独自の技巧を探究しテキスタイルアートの領域を拡大し、モニュメンタルな作品を作るに至った。
オルガ・デ・アマラルは1932年コロンビア、ボゴタで生まれ。1954年に政治変動のためアメリカのミシガンに移住。そこのアートスクールでテキスタイルデザインに出会う。ミシガンで出会ったポルトガル出身のご主人とその後ボゴダに戻り装飾テキスタルの会社を始める。60年代になって新しいテキスタイル技術を実験して異なる素材を混ぜて3次元的要素を導入した大規模な作品を作るようになる。1973年に奨学金を得てパリに滞在。81年にはパリ近代美術館でも大作が発表されるが、その割にはその後フランスであまり作品を大規模に発表される事はなかった。つまり今回のカルティエ財団の展覧会が初めての大回顧展で、 コロンビア以外では今まで発表されたことのなかった作品も数多く含めれている。
研究された「技術」に裏づけされた彼女の作品だが、それは幾何学的なモダンアートとともに南米の伝統的な色彩豊かな織物、それに中南米古代文化を思い起こさせる世界を作り出していることも目を引く。
特に下に掲載するビデオのような、通常は数学的で冷たい感じのするオプティックな効果をソフトな糸・布で再現し、自然な光や波のような親しい感じのものとしたのはとてもユニークだと思う。
作品解説でおおっと思ったのは、テキスタイルとテキストは「織る」と「物語る」という二つの意味を持つtexereを語源としていて、このことはすでにインカ文明が文字がわりに結び目で記録をしたことに現れている! でもラテン語語源だから我田引水みたいな気がするが、、、アマラルには一本の糸は一つの単語であり、コードを知った人しか理解できないインカの結び目文字の意味的表現を言及するとか、、、そういう難しいことは言わずもがなの直截的に理解可能な作品と思えるが、皆さんいかがでしょうか?
テキスタイルが醸し出す微妙な揺れとか現実に体感しないとわからない。写真じゃ全く伝わらないです。
かつまた今回は文句のつけようのないほど全作品美しく展示されている。私がこんなにカルティエ財団褒めたこと今までなかったんじゃないかい(大笑)